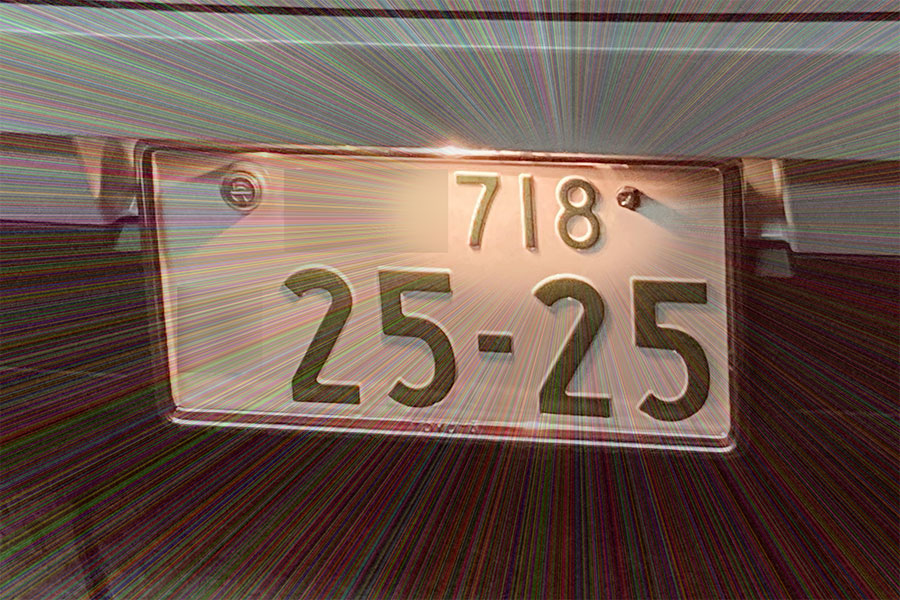アメリカより先行っていた!?「日本初の四駆」富士山の麓で快音を奏でた!「唯一無二のエンジン音、ぜひ聞いて」
読み込み中...
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
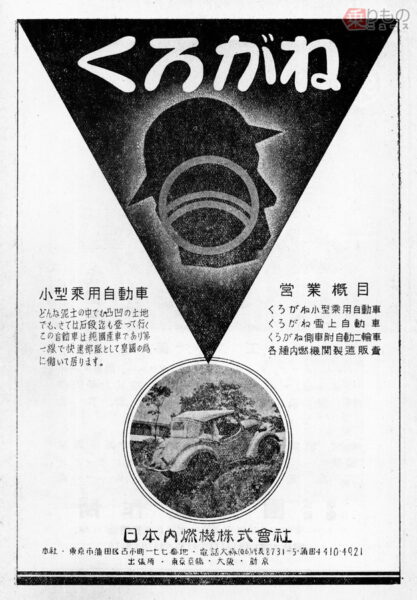 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像