「鉄道×戦闘機エンジン」国鉄がマジで試作した車両とは!? 雪との闘いに“豪快すぎる発想”で対抗した結果
読み込み中...
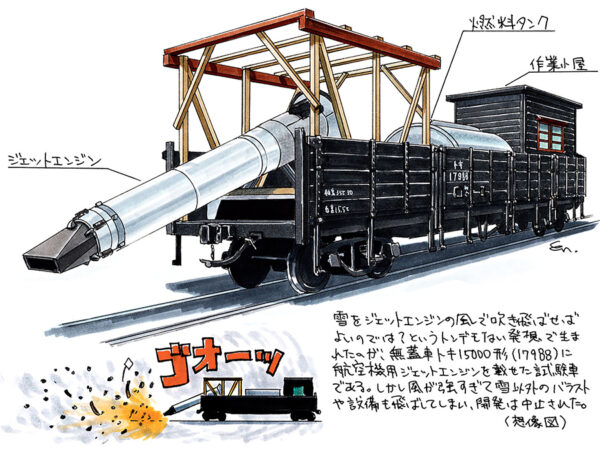 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
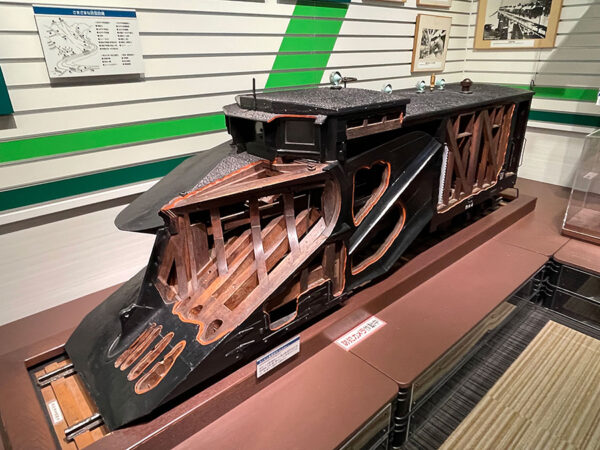 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像

 拡大画像
拡大画像





