“西日本最大の赤字路線”の「秘境ターミナル駅」へ行ったら“意外にも大賑わい”だったワケ 「す、座れない…!」
読み込み中...

 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
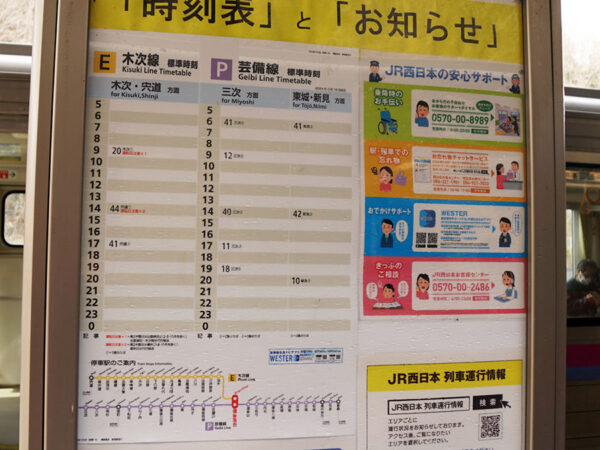 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
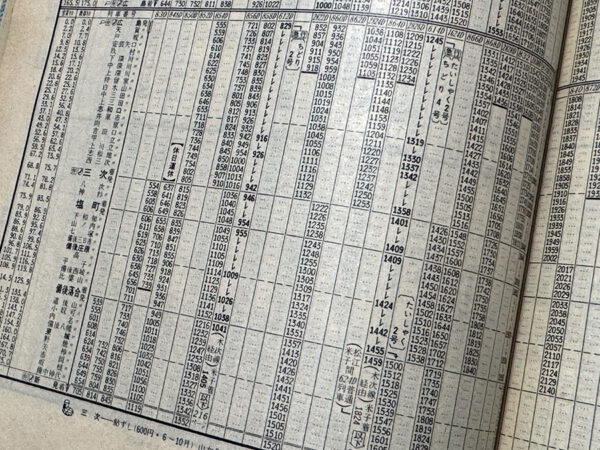 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
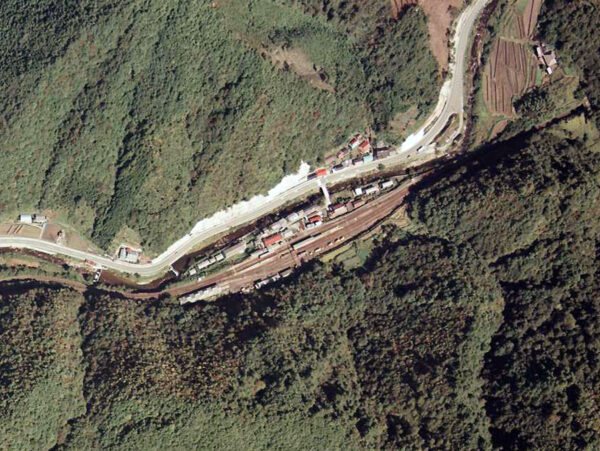 拡大画像
拡大画像




