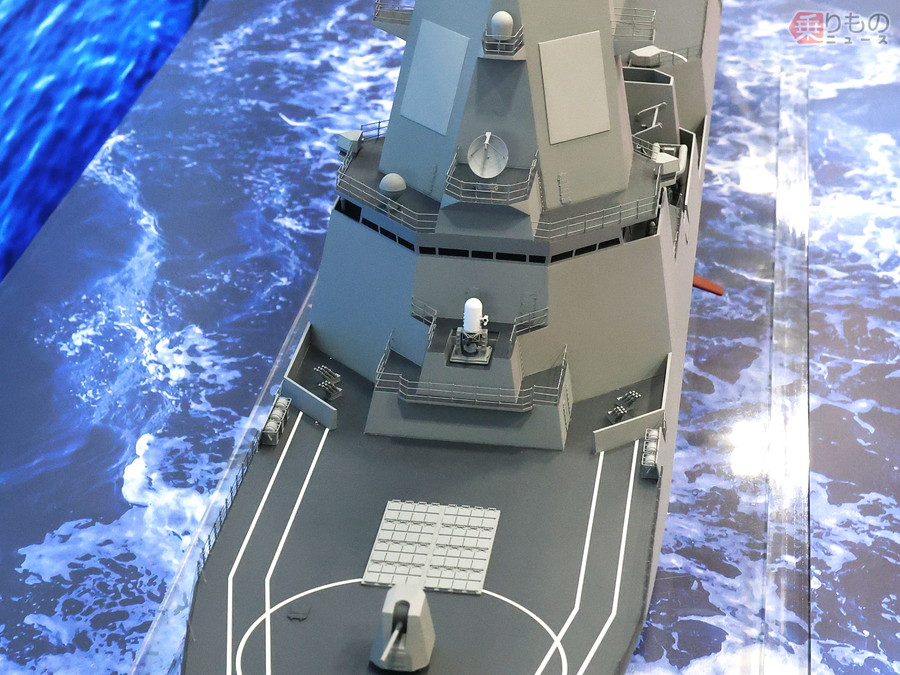「デカい! 高い!!」現存唯一「日本戦艦の砲塔」を実見 このたび現存が確認された部品も
読み込み中...
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
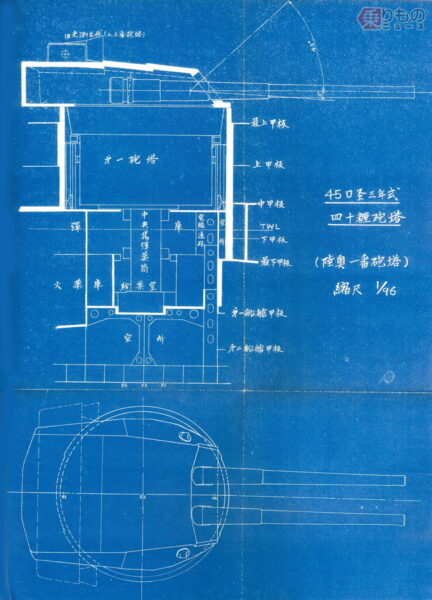 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像
 拡大画像
拡大画像