「ウンチから電気作りま~す」ダイハツの驚愕チャレンジどうやって? 将来はそれでクルマづくりの動力へ
ダイハツが、現在滋賀にある工場でバイオマス資源を活用するための実証実験をしています。昨年末から工場敷地内で「バイオガス実証プラント」を稼働させていて、将来的には製造に使用するエネルギーの地産地消を目指しているとのことです。一体どのようなビジョンを描いているでしょうか。
ちゃんと考えられた生産までの工程
ガスを作るために欠かせない、発酵槽を保管しておく「チャンバー」と呼ばれる入れ物にあたる設備は、常時37度に保たれているのですが、この熱原は、保温のためだけに電気や化石燃料などを行わず、滋賀工場から供給される仕組みになっています。実は、温度を保つ熱源はアルミ溶鉱炉の排熱が使われていて、捨てる熱エネルギーを無駄なく再利用しているのです。

また、チャンバーに関しても市販品を基に独自で開発・試作したもので、断熱材の配置などは手作り感にあふれています。なお、チャンバーの開発には自動車開発で使われる寒冷地試験設備が役立てられたそうです。
こうした発酵槽で生成されたバイオガスは「ガスバック」という袋に送られ、一時的に貯められることになります。
ダイハツは将来的にこのような過程で生成したバイオガスで、アルミ溶鉱炉を稼働させるのが目標ですが、現在の実証実験の規模では発電機の燃料として使用されています。担当者に話を聞くと「発電機のエンジンはこの滋賀工場で製造されたものです」との回答が。このようなポイントにも地産地消を感じさせます。
ちなみに現在は1日あたり約2トンの近江牛のフンを受け入れているそうですが、アルミ溶鉱炉を実際の製造で稼働させるには1日あたり約40トンが必要とのことです。
このように聞くと、思い描いているプランは現実的ではない印象を持つかもしれませんが、将来この構想を現実のものとしようとする際には、「より多くの酪農家の協力を得て、ほかに食品廃棄物を活用する方法も計画しています」と担当者は話します。
そして前述した通り、ガス生成時に余った発酵残渣は液肥や堆肥として役立てられるためのプロセスが行われます。残りカス「残渣(ざんざ)」を吸い上げ、個体と液体に分離し、液肥と堆肥に分けられるというのがざっとしたプロセスです。
この、発酵槽から残渣を吸い上げる過程では、自動車生産で使われるロボットが流用されていたり、固体の堆肥を次の工程へ流す箇所では工場で使わなくなった振動コンベアを使用していたりしています。
「エネルギーの地産地消」となると、非現実的なプランと感じてしまいますが、これまで培ったノウハウを投入し、既存である設備を使用したり、使わなくなった設備を再活用したりしている点を見ると、ダイハツはエネルギーの地産地消を現実的な将来プランとして見据えているのが強く伝わってきました。
Writer: 西川昇吾(モータージャーナリスト)
1997年生まれ、日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員。自動車専門誌やウェブ媒体、ファッション誌などで、新車情報からカスタムかー、旧車、カーライフお役立ちネタまでクルマに関して幅広く執筆。自身でのレース活動も行っている。




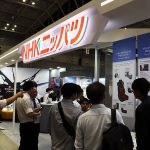
コメント