「ウンチから電気作りま~す」ダイハツの驚愕チャレンジどうやって? 将来はそれでクルマづくりの動力へ
ダイハツが、現在滋賀にある工場でバイオマス資源を活用するための実証実験をしています。昨年末から工場敷地内で「バイオガス実証プラント」を稼働させていて、将来的には製造に使用するエネルギーの地産地消を目指しているとのことです。一体どのようなビジョンを描いているでしょうか。
どうして? 作動しなくなる意外な理由
ダイハツが、現在滋賀にある工場でバイオマス資源を活用するための実証実験をしています。昨年末から工場敷地内で「バイオガス実証プラント」を稼働させていて、将来的には製造に使用するエネルギーの地産地消を目指しているとのことです。一体どのようなビジョンを描いているのか、現地取材で聞きました。

現在ダイハツが稼働させているバイオマス実証プラントは、「竜王町バイオマス産業都市構想」実現に向けた取り組みのひとつで、この構想はダイハツ側から竜王町へと提案し、動き始めたプロジェクトとなります。
ではなぜ、竜王町でバイオマス製造工場を作ろうとしたのか、それはバイオガスの入手経路が関係しています。同地は近江牛が名産のひとつとなっています。この近江牛のフン、つまり「うんち」を用いてバイオガスを作り、そのバイオガスをカーボンニュートラル燃料として溶鉱炉で燃焼して自動車部品製造時のエネルギーとして使うのが将来のビジョンです。なお、実証実験の現段階では発電機を稼働させています。
さらに、牛フンを使用しバイオガスを作ると、そのときに残ったカスのようなものである、発酵残渣(はっこうざんさ)を用いて堆肥や液肥を製造することもできます。こちらは有機肥料として活用して、近江牛が食べる飼料を作るのに役立てられます。このようにエネルギーの地産地消を目指すのが「竜王町バイオマス産業都市構想」なのです。
ダイハツ滋賀工場は自動車の生産だけでなく、エンジンやミッションなどの基幹部品も生産しています。エンジンブロックやミッションケースなど、アルミ鋳造で生産する部品が多く、その生産にはアルミ溶鉱炉が必要不可欠です。
アルミの溶解熱源は電気がよく使われますが、実はガスを燃焼する方が効率的でCO2の排出が少なく済むといわれています。それを地元で作ったカーボンニュートラル燃料で賄うことが出来れば、より環境に配慮した工場へと前進できるという訳です。
2024年末から稼働を始めたバイオマス実証プラントでは、自動車生産と開発で得たノウハウがふんだんに生かされているのが特徴で、ダイハツで開発した設備が多いのが印象的でした。
まず最大の特徴として近江牛のフンに合わせたダイハツ独自のメタン発酵技術を開発していることです。
一般的にバイオメタン発酵に使われるフンは乳牛のものが主流で、水分量が多いのに合わせた湿式発酵がオーソドックスな方式となっています。
対し、食肉として育てられることの多い近江牛のフンは水分量が少なく、さらに稲ワラやオガクズといった“しき料(牛の寝床に敷くもの)”が混入しており、従来のタンクに投入する湿式発酵には向いていません。
そこでダイハツではフンの脱水などの処置をあえてせずに、独自の乾式発酵プロセスを開発し、独自の乾式で約2週間での発酵が完了となる方法を作り出しました。なお、従来の湿式では、完了までに約1か月を要することが一般的です。




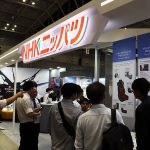
コメント