東京IC「1」横浜青葉「3-1」… 高速道路IC・JCT番号の法則 物語る過去未来
高速道路のICやJCTには、路線ごとに通し番号が振られています。そのなかには「3-1」「3-2」と枝番が付与されているものや、欠番になっているものも。これらから、路線の歴史や未来の計画がわかります。
「2」がない東名 そのワケは?
東名高速の場合は、起点側から東京IC「1」、東名川崎IC「3」、横浜青葉IC「3-1」、横浜町田IC「4」になっています。横浜青葉ICは、路線開通から30年経った1998(平成10)年に新設されたため「3-1」ですが、「2」が欠番になっているのはなぜでしょうか。
この「2」にあたるものとして、東京IC~東名川崎IC間で2020年現在、外環道と接続する東名JCT(仮称)の建設が進められています。外環道「東名~関越」区間の建設計画そのものは、東名が開通した1960年代から決定していたものの、長らく手付かずの状態でした。
ちなみに中央道でも「2」は欠番となっており、「1」の高井戸ICと、「3」の調布ICのあいだで、外環道が接続する中央JCT(仮称)の建設が進められています。
このように、すでに開通済みの区間で欠番が存在する例はほかにもあります。また、すべての路線で「1」から通し番号が始まるとも限りません。たとえば名神高速は東名から連続した番号が振られていて、小牧ICの「24」から始まり、終点の西宮ICは「38」です。
【了】



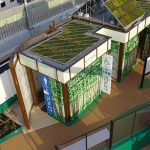

枝番の方は度々スライドあり。
裾野ICとか、浜松西ICとか、秦野中井ICとか、
上り方にJCTやらSICやらが出来ると順送りで枝番が大きくなる。
まあ、子枝番、孫枝番とか増やされるよりはマシか(笑)
そう言えば、廃止による欠番ってないのかな?