「水素で走る大型トラック」普及のカベは? 「スペック的には有能」でもEV車とは事情が違う
JMS2025において三菱ふそうが公開した水素で動く新しい大型トラック(10t車)のコンセプトモデル「H2IC」と「H2FC」。どのような性能で、普及にはどのようなカベがあり、
水素燃料の問題点の解消を目指すには?
10月29日から11月9日まで東京ビックサイトで開催された「ジャパンモビリティーショー2025(JMS2025)」において、三菱ふそうトラック・バス株式会社(以下、三菱ふそう)は、水素で動く新しい大型トラック(10t車)のコンセプトモデル「H2IC」と「H2FC」を展示しました。

現在、環境負荷の低減と世界的なエネルギー・トランジションの流れから、ガソリンなどの化石燃料を使わない自動車の開発・普及が進んでいます。電気で動くEV(電気自動車)は乗用車のカテゴリーで一定の成功を収めていますが、バッテリー重量や充電時間の問題から長距離輸送に使われる10t車サイズのトラックで製品化されたものはまだ存在していません。
その、EVにかわって注目されているのが水素燃料です。車体の専用タンクに圧縮水素ガス(CGH2)を充填し、それを燃料電池スタックで化学反応させて発電してモーターを駆動させます。すでに乗用車サイズではFCEV(燃料電池車)としてトヨタ「ミライ」やホンダ「クラリティ フューエル セル」が実用化されており、全国にも補充用の水素ステーションが整備されています。
しかし、今回展示された「H2IC」は、この圧縮水素ガスを使い、それを発電ではなくエンジンで燃焼させて駆動させる水素燃焼エンジン車であることが特徴です。車体には58kgの圧縮水素ガスが充填でき、試作車での航続距離は700kmにもなります。
また、設計値では全国に普及している水素ステーションが利用でき、車体内部の機器も約80%をディーゼルエンジンの車両からの流用可能で、実用化されれば既存の流用をすることで、導入時のコストの低下が期待されています。




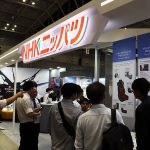
日野自動車はFCトラックを既にラインオフしていますよ。
文中に見られる「科学反応」、どう考えても「化学反応」の誤用です。
ご指摘ありがとうございます。
記事を修正いたしました。