「水素で走る大型トラック」普及のカベは? 「スペック的には有能」でもEV車とは事情が違う
JMS2025において三菱ふそうが公開した水素で動く新しい大型トラック(10t車)のコンセプトモデル「H2IC」と「H2FC」。どのような性能で、普及にはどのようなカベがあり、
水素の問題点と現状
しかし、水素トラックがまだ実用化されていないことからも分かるように、水素にもまったく問題がないワケではありません。一番の問題は圧縮水素ガスを供給する水素ステーションが全国で約160カ所(2025年現在)しかない点です。

いかに性能的に長距離を走れても、運行するルート上にガソリンスタンドのように水素ステーションがなければ、業務で利用することができません。水素ステーションの数が少ない理由は、それを利用する水素自動車の数が少ないことと、設備費用が1カ所あたり約5億円も掛かることだと言われています。
また、車両的にも水素ガスが気体であるためにタンクの容積が必要で、「H2IC」では700kmという航続距離を実現するために8本ものタンクを車内に積載しており、トラックとしての貨物スペースを圧迫すると問題もあります。
性能的にディーゼルエンジンのトラックと同じであっても、実際に運行するには改良やインフラ面での対応がまだまだ必要なのです。
この問題に関しては、改善の試みが続けられており、現状の圧縮水素ガスの問題点を解消するために、新しいサブクール液体水素(sLH₂)という規格を採用した水素トラックが「H2FC」になります。
サブクール液体水素は通常の液体水素(約-253℃)よりもさらに数度低い温度で保持される「過冷却液体水素」で、蒸発損失を抑える利点があります。
この保存法の場合水素は気体ではなく液体のため、面積あたりのエネルギー密度が高く、これによって動力源として効率が良いだけでなく、それを充填するタンクを削減することができます。実際、水素を気体で保管する「H2IC」では8本ものタンクが必要でしたが、液体の「H2FC」ではシャーシ内に2本のタンクだけ対応でき、走行距離も1200kmと長くなっています。
また、水素ステーションの設備も、圧縮水素ガスでは気化器や圧縮機といった複数の機材が必要でしたが、液体水素では専用の貯蔵槽に保管するだけよく、導入と運用コストの大幅な低減が可能だと言われています。




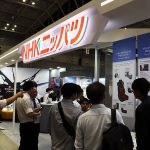
日野自動車はFCトラックを既にラインオフしていますよ。
文中に見られる「科学反応」、どう考えても「化学反応」の誤用です。
ご指摘ありがとうございます。
記事を修正いたしました。