「フェアレディZの父」こそ社長に相応しかった! ゴーンすら染まった日産の「負の連鎖」とは
業績が急速に悪化した日産。しかし不振を繰り返した背景には、社内に蔓延る官僚主義とそれに起因する独裁があったのではないでしょうか。日産に多大な貢献をした「フェアレディZの父」を冷遇したことが間違いでした。
正当な評価を得られなかった「フェアレディZ」の父
かつて「技術の日産」と呼ばれていた同社には、数多くの優秀なエンジニアがいました。しかし、彼らがいかに実績を残そうとも、政治力がものをいう社風では社長になることは難しいのが実情で、役員に取り立てられることさえ稀でした。事実、川俣氏以降の10人の日産社長のうち、技術畑出身は久米 豊氏と辻 義文氏、現CEOであるエスピノーサ氏の3人だけです。

ただ、このような日産ですが、過去、本来なら社長に就任してもおかしくないほどの経営能力と実績を持っていた人物がいなかったわけではありません。それは「ミスターK」こと片山 豊氏です。彼は技術者ではなく販売の人間でしたが、自他ともに認めるカー・ガイ(カーマニア)で、クルマの良し悪しを見抜く能力に秀でていました。
その経歴をひも解くと、片山氏は1935年に日産へ入社。宣伝を担当したのち、国策会社の満州自動車へと出向しています。
終戦後は日産に戻り、再び宣伝を担当すると、その際に国内自動車メーカーに働きかけ、1954年に「第1回東京モーターショー」(当時の名称は「全日本自動車ショウ」)の開催に尽力しています。そこれショーに出展するため、軽自動車の元祖となる「フライングフェザー」を住江製作所(現・住江工業)で仲間と生み出し、のちに200台製造する実績を残しています。さらに彼は、1958年にオーストラリア・ラリーへ参戦し、初参加ながら1000cc以下クラスで優勝する快挙も成し遂げました。
ところが、その活躍が嫉妬を買い、片山氏は日産社内で冷遇されるようになりました。社内で居場所がなくなった彼は北米への赴任を命じられます。当時の日本の自動車産業は実力不足もあって海外市場をまったく重視しておらず、この人事は体の良い島流しだったと言えるでしょう。
しかし、渡米した片山氏は改革に着手し、支社のあったニューヨークとは別にカリフォルニアに現地法人を設立すると、商社を頼ることなくダットサン・ブランドの販売・サービス網を構築し始めました。そして、自ら個人経営の中古車店に飛び込み営業をかけ、「まずはアンタが儲けろ。我々はそのあとで良い」といったハナシで店主を口説き落とし、代理店を増やしていきます。
まずは安価なピックアップトラックで販売の足がかりを築くと、経営が安定したところで高性能と価格の安さを武器にダットサン「410」や「510」(日本国名では「ブルーバード」名で販売)で販売拡大を実現しました。




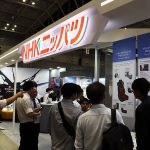
コメント