「フェアレディZの父」こそ社長に相応しかった! ゴーンすら染まった日産の「負の連鎖」とは
業績が急速に悪化した日産。しかし不振を繰り返した背景には、社内に蔓延る官僚主義とそれに起因する独裁があったのではないでしょうか。日産に多大な貢献をした「フェアレディZの父」を冷遇したことが間違いでした。
日産復活の鍵は「カー・ガイ」を正当に評価すること
北米での経験を通じて、若者向きの安価なスポーツカーの必要性を痛感した片山氏は、腰の重い日産本社を粘り強く説得し、ロングノーズ・ショートデッキ、クローズドボディの「フェアレディZ」を開発させます。このクルマが爆発的にヒットしたことで、北米で「ダットサン」の名を定着させると、フォルクスワーゲンを抜いて日産/ダットサンを輸入車のトップブランドへと押し上げることに成功したのです。

こうして北米市場を開拓し、日産本社を大いに潤わせた片山氏でしたが、17年におよぶ北米勤務を終えて帰国すると、待っていたのは子会社の役員という多大な功績に見合わないポストでした。
当時、社長を務めていた石原氏は、かつては輸出部門の責任者という地位にあったため、片山氏の活躍を逆に快く思っていなかったとか。そのような私怨からか、日産は1981年以降、段階的にダットサンを廃止し、ブランド統一を図ることを発表します。北米では圧倒的な知名度を誇り、多くのファンを育ててきたダットサン・ブランドを自ら手放したのは日産にとっては失敗であり、あまりにも愚かな決定でした。
フランクな性格の片山氏は、日産退任後もアメリカにおいて「ミスターK」あるいは「Z-carの父」として慕われ続け、カーイベントのゲストとしてたびたび出席するなど精力的に活動して多くのファンと交流を深めました。それらが実を結び、1998年には本田宗一郎氏に続いて日本人ふたり目となる米国自動車殿堂入りを果たすまでに至っています。
片山氏の実績と能力が正当に評価される社風であれば、日産は何度も経営危機を繰り返すようなことはなかったことでしょう。筆者(山崎 龍:乗り物系ライター)が思うに、まずは社内から官僚主義と腐敗を一掃すること。そして、彼のようなカー・ガイが活躍し、相応の地位を得て活躍できる環境を作ること、それこそが日産復活のための第一歩なのではないでしょうか。
Writer: 山崎 龍(乗り物系ライター)
「自動車やクルマを中心にした乗り物系ライター。愛車は1967年型アルファロメオ1300GTジュニア、2010年型フィアット500PINK!、モト・グッツィV11スポーツ、ヤマハ・グランドマジェスティ250、スズキGN125H、ホンダ・スーパーカブ110「天気の子」。著書は「萌えだらけの車選び」「最強! 連合艦隊オールスターズ」「『世界の銃』完全読本」ほか」に




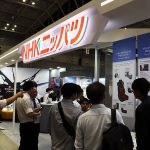
コメント