ぐるぐる回るセンサーがない!? 日産が公開した自動運転車両“ココが違う!”その性能とは?
日産グローバル本社ギャラリーにて、自動運転モビリティサービスの実証実験に使用される車両が公開されました。ベース車両は日産の「セレナ」ですが、どのような特徴があるのでしょうか。担当者に話を伺いました。
ぐるぐる回らないセンサーである意味とは?
2025年10月3日、日産グローバル本社ギャラリーにて、自動運転モビリティサービスの実証実験に使用される車両が公開されました。ベース車両は日産の「セレナ」ですが、どのような特徴があるのでしょうか。担当者に話を伺いました。

まず全体のフォルムで目を引くのは、一般的な自動運転車に見られるような、360度回転するLiDAR(ライダー)センサーが目立つ位置に搭載されていない点です。もちろん、日産のこの車両もセンサーによってさまざまな情報を収集していますが、その仕組みがやや異なるとのことです。
担当者によると、「この車両は、ルーフに一つのセンサーを設置して全体を監視するのではなく、車体の四方に設けられた鏡のような形状のセンサーが、LiDARとしての役割を果たしています」とのこと。さらに、回転式との違いについては、「遠距離の情報を高精度で収集するのに適しています」と説明してくれました。
この鏡型センサーは、セレナの高めの車高と組み合わせることで、検出エリアを大幅に広げることができ、より高精度な情報の取得が可能になるそうです。ただし、主に遠距離の情報収集に特化しています。
そのため、足元や車両のすぐ近くにある物体を検知するため、サイドミラー付近には回転式のLiDARが別途設置されているとのことです。これら2種類のセンサーを組み合わせることで、長年の研究を経て進化したAIが、車外環境の認識や行動予測による判断・制御を行い、よりスムーズで“優しい”走行を実現しているといいます。
この「優しい自動運転」は、テスト走行時にも高く評価されており、担当者は「中国やアメリカで乗った自動運転タクシーよりも乗り心地が良かったという声をいただきました」と語ります。日産では2017年から自動運転の研究を開始しており、ハンドルの切り方や加減速の仕方など、人間が快適だと感じる運転挙動についても検証を重ねてきました。その成果が、今回の評価につながっているようです。
また、緊急時の判断能力も高く、緊急車両への対応や、横断歩道における歩行者への配慮なども、収音マイクやセンサー、カメラを駆使して的確に行えるとのこと。実際に警察の運転審査官が試乗した際には、「これなら試験に一発合格ですね」とお墨付きを得たそうです。ちなみに、教習所を経ずに一発試験で合格する確率は5〜10%程度といわれており、それを踏まえると、AIの運転技術の高さがうかがえます。
ただし、このように周囲に細やかに配慮した走行に対し、「運転がややトロい」と感じる人もいたようです。その点について担当者は、「自動運転が普及すれば、電車に対して『遅い』とか『危険では?』と思う人が少ないのと同じように、“そういう乗りものなのだ”という認識が広がっていくはずです」と話し、公共交通機関としての受け入れが進めば、評価も変わっていくだろうと見解を示しました。
同車を用いた実証実験は2025年11月27日から2026年1月30日まで横浜市みなとみらい周辺で実施されます。運行台数は5台で、計26か所の乗降エリアが設置される予定です。なお、一般利用モニターの募集期間は10月3日から10月31日までで、実証実験の該当エリアを通勤などで利用している人に限定されます。




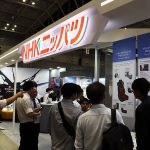
コメント