旧海軍「航空魚雷」秘密のパーツはベニヤ製!? 米軍驚愕の高速雷撃はどう実現したのか
現代では姿を消した兵器のひとつ「航空魚雷」は、WW2期までは文字通り先端技術の結晶です。旧日本海軍においても実用化は相応の困難をともなうものでしたが、その一端を担ったのは、ベニヤ製のごく簡単な構造のパーツでした。
「航空魚雷」のなにがそれほど難しかったのか
日本海軍はこの航空魚雷への取組みを、1914(大正3)年に呉の海軍工廠で、クレーンに吊るした魚雷を海面に落下させるという実験から始めています。1915(大正4)年には100馬力のモーリス・ファルマン水上機に重さ約330kgの36センチ魚雷を積んで飛行実験を行いましたが、離水するのがやっとという状態でした。
それでも航空機の発達は早く、1922(大正11)年には日本初の雷撃機で、重さ約550kgの18インチ魚雷を搭載できる「十年式艦上雷撃機」が完成します。十年式は揚力を稼ぎつつも狭い空母で場所を取らないように、主翼が3枚という珍しい三葉式を採用しました。しかし単座であるなど使い勝手が悪く生産は20機で終わり、後継の「一三式艦上攻撃機」に引き継がれます。

その後、雷撃機は高性能になり大馬力高速化しますが、雷撃するには逆になるべく低速、低高度で投下した方が命中率は高くなるという、相反する要素をいかに統合するかが課題でした。海面の状態は凪から荒天まで様々で、魚雷の定針を確保するのも難題です。これらを解決するには航空魚雷の技術革新も必要だったのです。
1935(昭和10)年末以降、横須賀海軍航空隊(横空)雷撃班では、空技廠と共同で魚雷発射実験を繰り返していました。そうしたなか1936年から1937年ごろ、前述したベニヤ製パーツ「框板(かまちいた)」が開発されます。
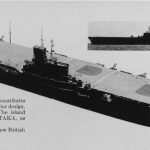




コメント