「名前のルール、変えないで」欧州車の“シンプルすぎるモデル名”に生じた混乱 そもそもなぜ愛称ないの?
クルマの命名法を「変えます」「やっぱり元に戻します」――独アウディの方針転換に世界のユーザーが混乱しているようです。アルファベットや数字で表される輸入車の車名は、本来どのようなメリットがあるのでしょうか。
なんで名前そんなにシンプルなの?
アウディのようなアルファベットと数字を組み合わせた規則性のある命名法は、欧州メーカーに多く採用されている方法です。メルセデス・ベンツ、BMW、プジョーなどが筆頭で、日本ではマツダが採用しています。

一方、トヨタなどの日系メーカーや、アメリカ系メーカーの多くは、1台ずつに個別の名称を与える方式、いわゆるペットネームを採用しています。この2の方法は、それぞれにメリットがあります。
アルファベットと数字を組み合わせる規則性の命名法のメリットは、命名のルールさえ理解すれば、名前を聞くだけで、どんなクルマであるかを即座にイメージすることができます。
たとえば、アウディの「A1スポーツバックTFSI」とあれば、低い床(A)の、ハッチバック5ドア(スポーツバック)で、ガソリン・エンジン(TFSI)を積んでいることを示します。
メルセデス・ベンツならば、最初に車格と車型を示すアルファベットがあり、それにパワーを示す数字が続きます。「A」「C」「E」「S」などが車格で、アタマに「GL」とあればSUV、「CL」が4ドアクーペ、「EQ」なら電気自動車です。「GLA」ならば、車格がAのSUVとなるというわけです。
BMWは基本的に3桁の数字でモデル名を示します。3桁のうち、最初の数字が車格で、後ろの2桁がエンジン排気量・出力を意味します。また、最初の数字の偶数はスポーティなモデル、奇数が通常モデルで、数字が大きいほどサイズが大きくなります。ベストセラー車のひとつ「320d」ならば、3シリーズで2000ccのディーゼル(d)エンジンを積んだモデルです。SUV系はX、ロードスター系はZ、電気自動車はiが使われています。
マツダの場合は、セダンとハッチバックは1桁の数字のみで、数字が大きいほど車格が上がります。そしてSUV系にはCXに車格の数字を組み合わせたものが使われています。




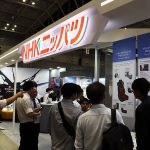
コメント