「名前のルール、変えないで」欧州車の“シンプルすぎるモデル名”に生じた混乱 そもそもなぜ愛称ないの?
クルマの命名法を「変えます」「やっぱり元に戻します」――独アウディの方針転換に世界のユーザーが混乱しているようです。アルファベットや数字で表される輸入車の車名は、本来どのようなメリットがあるのでしょうか。
実はカネがかかる“日本方式”
面白いのは、アウディもメルセデス・ベンツもマツダも、すべてのモデルでグリルのイメージが統一されていることです。マツダの開発者は「個別のモデルではなく“マツダそのものを知ってほしい”からデザインを統一している」と説明していました。

つまり、アルファベットと数字を使う命名法の場合、モデルごとではなく、ブランド全体をアピールするのに向いていると言えるでしょう。ブランドの価値を高めるのには、よい方法だと思います。
それに対してペットネームは、個々の個性を強くアピールすることに向いています。雰囲気を変えてペットネームを差別化すれば、同じセグメントのモデルを2つ売ることができます。
たとえばトヨタの「ハリアー」と「RAV4」。ほぼ同じサイズのSUVですが、「ハリアー」は洗練された街乗りクルマ、「RAV4」はアウトドアが似合うアグレッシブなクルマという住み分けができます。ペットネームを使うことで、個性豊かなクルマを売ることができるのです。
一方で、それぞれデメリットもあります。
ペットネームは個性を感じさせることができますが、その一方で、名前を聞くだけでは、そのクルマがどんなサイズで、どんなキャラクターで、どんな車型なのかがわかりません。お金と時間をかけて、しっかりとプロモーションを行う必要があるのです。これがデメリットとなります。
アルファベットと数字の組み合わせの場合は、個々のモデルの個性を押し出しにくいのがデメリットになります。もしも同じ顔つきのデザインにしてしまうと、ラインナップの違いはサイズのみとなってしまい、それぞれの個性が強く感じられません。
そして、今回のアウディの騒動のように、命名法のルールを崩すと、混乱が生まれてしまうのも課題です。ユーザーが命名のルールを理解しているから、名前だけで姿がイメージできるのに、命名法のルールが揺らぐとわからなくなります。これが大きなデメリットです。
アルファベットと数字の規則性を使うのも、ペットネームを使うのも、どちらにもメリットとデメリットが存在します。どちらが勝ちというわけではありません。だからこそ、クルマ100年の歴史で、どちらも存続していると言えるでしょう。
Writer: 鈴木ケンイチ(モータージャーナリスト)
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員。自動車専門誌やウェブ媒体にて新車レポートやエンジニア・インタビューなどを広く執筆。中国をはじめ、アジア各地のモーターショー取材を数多くこなしている。1966年生まれ。




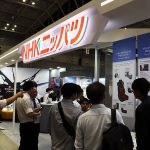
コメント