スゴ腕戦闘機パイロットが生み出した「最強の空戦理論」とは? じつは民間機にも活用されています
現代の戦闘機パイロットが教科書のように用いる空戦理論があります。それを生み出したのは米軍の戦闘機パイロットですが、彼は実戦では戦果を出したわけではないとか。ただ、民間機パイロットも基本にしているそうです。
「空戦必勝法」を理論で整理
エネルギーを失ってしまう大きな要素は、旋回や上昇などで発生するG(重力加速度)です。Gは空気抵抗によるブレーキの側面があるので、急旋回で大きなGをかけてしまうと、高度を上げなくても速度を落としてしまい、結果としてエネルギーの総量が小さくなって不利になるというワケです。
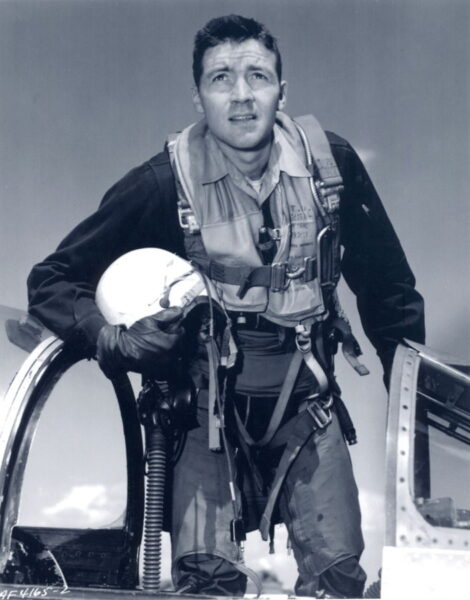
このため、空戦を有利に戦うためにはスロットルを開けて加速し続け、エネルギーを減らさないよう適切なGをかけながら動き回ることが必要となります。これまでエースパイロットの肌感覚だけに頼っていた「空戦必勝法」が、誰にでも理解できる理論となったことで、戦闘機パイロット養成のプログラムは飛躍的に進歩したのでした。
E-M理論は同時に、空戦における戦闘機の飛行特性を比較することにも応用できました。結果、最高速度は速くても加速までに時間がかかっていたり、小回りが利いても遅い速度域だけだったりなど、性能諸元(カタログスペック)だけではわからない、実際の空戦機動における性能を一定の基準で評価できるようにもなりました。
戦闘機の空戦性能評価に使えるということは、E-M理論を設計段階で組み込めば、最強の空戦(格闘戦)能力を持つ戦闘機を作ることも可能になります。ボイドは理想の戦闘機を実現すべく、空軍内の同志とともに「戦闘機マフィア」と呼ばれるグループを結成し、空軍上層部に働きかけるようになりました。
彼らが理想としたのは、ベトナム戦争でのデータから格闘戦が行われるのはマッハ1以下であることが多いことを踏まえ、最高速度はマッハ1.6程度、軽量で操縦性が良く、推力重量比の大きな加速性に優れた戦闘機でした。
当時進んでいたF-15の開発ではプレゼンが成功しなかったものの、F-15が高コストの機体となって調達ペースが落ちたことから、国防長官が低コストで済むボイドらの戦闘機案に興味を示し、1970年代初頭に「軽量戦闘機(LWF)計画」がスタートします。





コメント