最近減った?「マツダの商用1BOX車」じつは違う顔で販売中!「でも、オリジナルではありません」←どういうこと?
かつてはワンボックス車の代名詞ともなったマツダ「ボンゴ」は、日産や三菱、さらにはフォードにもOEM供給していました。しかし、マツダの戦略転換で今ではダイハツ車ベースになっています。
自動車メーカーが他社から商用車のOEMを受け入れる理由
かつて、ワンボックス車の代名詞となっていたマツダ「ボンゴ」は、さまざまなブランドにOEM供給していたことでも知られています。しかし、マツダが商用車生産から撤退したことにより、OEM供給をする側から受ける側へと転じ、現行型「ボンゴ」はダイハツからのOEM車となりました。そのような数奇な運命を辿った「ボンゴ」シリーズを今回は紹介します。

そもそも、OEMとは「Original Equipment Manufacturing」の略で、日本語では「相手先ブランド製造」と訳されます。OEMの目的を大まかにまとめると以下の3つになります。
1、市場が黎明期もしくはニッチ市場において、特定のジャンルの商品や製造技術を持たないメーカーが、他社からOEM供給を受けることでそうした市場へ参入しやすくなるほか、自社ラインナップの補完ができる
2、市場が成長期、自社の生産能力が追いつかない、あるいはラインナップを拡大する際に、他社製品を用いることで自社のラインナップを補強する
3、市場の衰退期に、開発・製造コストなどの問題から自社での独自開発・生産を止め他社製品の供給に切り替えることで、低コストで市場への製品供給が可能となる
メーカーを跨いだOEMで多いのが商用車で、理由は主に前出の(1)と(3)になります。日本車の場合、30年ほど前まで各社とも独自設計の商用バンや小型トラックを製造販売していました。
ところが、業務で使用する商用車の場合、最大積載量やボディサイズ、販売価格が決まってしまえば、自ずと性能は似たようなものとなり、他社との差別化が難しい、言うなれば「没個性」の選ぶところがない商品となってしまいます。
こうした車を、多額の費用を投じて自社開発するのは、金銭的にも開発リソースの面でもムダです。そこで販売力の劣るメーカーから、商用車についてはOEMモデルの導入が進みました。
ただ、商用車はメーカーにとっては利幅の薄いモデルですが、ディーラーにとっては法人などのフリートユーザーによる定期的な代替えが期待できる重要な商品です。また、商用車の購入などを通じて自社の乗用車を経営者や社員などに売り込むチャンスにも繋がります。
そのため販売現場では疎かにできない重要モデルでもあり、自動車メーカーのラインナップに不可欠な商品であることは間違いありません。




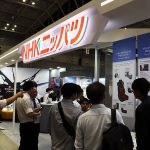
コメント