爆撃機が戦闘機みたいに“ミサイル発射!?” 米で浮上の「空飛ぶ武器庫」改修案とは? 背景に中国の脅威
アメリカ空軍の次世代ステルス爆撃機「B-21 レイダー」を、全翼機型アーセナル(弾薬庫)機にする構想が浮上しています。爆撃機に戦闘機の役割を担わせようとするものですが、二つの要因がこのアイデアを後押ししています。
技術的には可能でも課題は多く残る
B-21全翼機型アーセナル機は単独で行動するわけではなく、戦闘機や無人機と協調して情報ネットワークと長射程兵器を軸にして機能分担をするようです。
報道で示される案では、全翼機にAIM-260のような長射程空対空ミサイルを多数搭載し、F-22やF-35、将来のF-47のような有人戦闘機や無人機が目標を検出・指定すれば、全翼機型アーセナル機が長距離から空対空ミサイルを遠隔で発射するという運用が想定されています。
戦闘機自体がミサイルを搭載する必要はなく、つまりB-21全翼機型アーセナル機はセンサーとネットワークを介した空飛ぶミサイル発射機、文字通りの「弾薬庫」機というわけです。
しかし、技術的に可能であっても課題は多く残ります。まず、ステルス性と搭載兵装のトレードオフです。多数のミサイルを内蔵あるいは外付けで搭載する方法は、ステルス性を損ない被発見のリスクを高めます。
次にセンサーとデータリンクの脆弱性です。アーセナル機は戦闘機のセンサーに依存して遠隔発射する前提のため、敵の電子戦や妨害で通信が断たれれば役割を果たせません。ステルス技術や電子戦はアメリカの専売特許ではなく、中国の対ステルス能力、電子戦能力も急速に強化されています。
さらに生産数とコストの問題もあります。空軍グローバル・ストライク・コマンド(AFGSC)はB-21を戦略的爆撃力として要求しています。アーセナル機用途のために爆撃力を割くのか、あるいは生産数を増やすのか、専用の廉価なプラットフォームや無人機ではできないのか、空軍内部でも意見が分かれています。B-21関連予算を増やそうという政治的野心も見え隠れしています。
無人化・自動化・ネットワーク化・長射程兵器といった現代の要素は、過去にはなかった戦術を期待させます。しかし実際の運用では、戦闘の後方空域とはいえ大型のプラットフォームが空対空戦闘に加わることで、運用の足かせになるリスクはYB-40の場合と同じようにも思われます。敵も長射程空対空ミサイルやセンサー、ネットワークを保有しているのです。
爆撃機が戦闘機の任務を本当に兼任できるのか。そもそも無人機、ネットワークの時代に戦闘機、爆撃機という区分発想が時代遅れなのか。戦闘機とは呼ばず「全翼機型アーセナル(武器庫)機」というネーミングは言い得て妙ですが、最終的には技術的可能性と実戦での耐性(レジリエンス)、そして政策的選択のバランスが鍵になりそうです。
Writer: 月刊PANZER編集部
1975(昭和50)年に創刊した、50年以上の実績を誇る老舗軍事雑誌(http://www.argo-ec.com/)。戦車雑誌として各種戦闘車両の写真・情報ストックを所有し様々な報道機関への提供も行っている。また陸にこだわらず陸海空のあらゆるミリタリー系の資料提供、監修も行っており、玩具やTVアニメ、ゲームなど幅広い分野で実績あり。


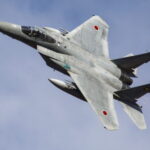


コメント