「えっ、庄内に台湾便!?」好調インバウンドの波に乗れない“幻の海外路線” ローカル空港の復活を阻む“定期便化の壁”とは
コロナ禍以前、山形県の庄内空港など意外な地方空港にも国際線がありました。しかし、訪日客が急回復するなかでも、これら“幻の路線”の復活は簡単ではありません。なぜでしょうか。
では、どうすればよい? 復活への「3つの処方箋」
この高い壁を乗り越えるには、従来の発想の転換が必要です。
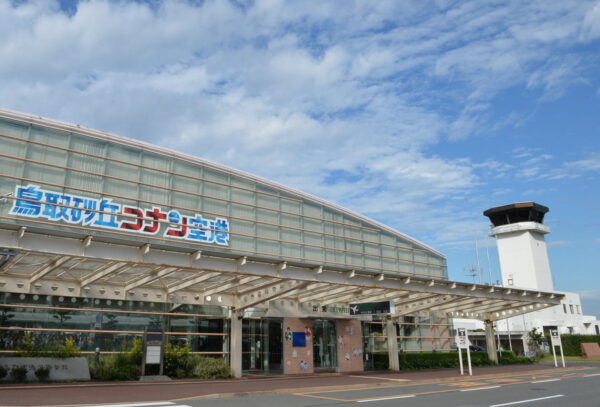
第一に、「人」への投資です。航空会社への補助金だけでなく、グランドハンドリング人材を地元の専門学校と連携して育成したり、空港職員の住宅を補助したりするなど、地域全体で空港を支える「空港エコシステム」を構築する視点が求められます。
第二に、「経営」の視点です。高松空港の成功事例のように、民営化による機動的な投資や官民連携は大きな力になります。自治体側も、単に観光地の魅力をアピールするだけでなく、航空会社の言語といえる収益性データに基づいた事業計画を提示し、対話を重ねることが重要です。
そして最も重要なのが、「アウトバウンド需要」の育成です。インバウンド頼みではなく、地域の姉妹都市交流や企業の海外進出支援などを通じて、地域住民や地元企業の海外渡航を能動的に創出すること。これこそが路線の安定化に直結するものであり、航空会社にとって最大の安心材料となります。
ただし、こうした「処方箋」も万能ではありません。庄内空港や松本空港のように滑走路に制約があるところは、まず近距離アジア路線から着実に実績を積むべきでしょう。一方、高松空港のように基盤のあるところは、既存路線のさらなる磨き込みが求められます。
地方空港の国際線復活は、単に飛行機を呼ぶことではなく、持続可能な「双方向の架け橋」を各地域の現実に合わせて地域全体で築き上げるものであり、そういった観点では自治体を含む当該地域における長期的な戦略が問われていると言えるでしょう。





飛行機に「今は亡き」は不適切な用法の気がします。
高松空港よりも仙台空港の方が民営化してから成功しています。
事例で上げるなら高松よりも仙台の方が良いのでは?