ロジスティックから見たハワイ攻略 真珠湾攻撃と「その先」 旧日本軍の手は届いたか?
真珠湾攻撃はそもそも、ハワイまで有効な打撃力を派遣できるかどうかすら不明な状況から始まりました。その先に考えられていたハワイ占領は、そもそも可能だったのでしょうか。ロジスティック面から真珠湾攻撃のその先を考察します。
かくて真珠湾攻撃は成った その後の戦略は…?
アメリカは日本の外交暗号の多くを解読していましたが、12月に入っても第一航空戦隊(「赤城」「加賀」)と第二航空戦隊(「飛龍」「蒼龍」)の所在はつかんでいませんでした。またアメリカ海軍内では、日本軍によるハワイ攻撃が想定されていたものの、そうしたリスクを承知の上でか否か、アメリカ政府は日本への外交的圧力を強化するため、太平洋艦隊を本拠地のサンディエゴからハワイに前進させていました。
かくして1941(昭和16)年12月7日の真珠湾攻撃は成功し、集結していた太平洋艦隊に大打撃を与えて、日本海軍機動部隊はハワイ航路から凱旋したのです。
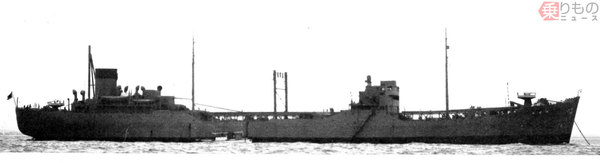
勝利への隘路 ハワイを占領せよ!
日本の戦略には、憧れのハワイ航路の制空権、制海権を得ることが必須でした。第一段作戦(南方作戦)の成果を防備拡大するため第二段作戦(オーストラリア占領、米豪遮断、ハワイ占領)が企図されます。
第二段作戦のタイムスケジュールは、1942(昭和17)年5月に東部ニューギニアのポートモレスビー攻略作戦(MO作戦)、6月にミッドウェー攻略作戦(MI作戦)、アリューシャン攻略作戦(AL作戦)、7月にフィジーおよびサモア攻略作戦(FS作戦)、10月にハワイ攻略作戦というものでした。運命のMI作戦にはミッドウェー島攻略のほかに、制空権、制海権を確保するためのアメリカ空母殲滅という、ふたつの目的がありました。
この稀有壮大な第二段作戦が日本勝利の分水嶺でした。ロジスティクス面からもハワイ攻略までが攻撃の限界点であり、ハワイ占領という衝撃をアメリカに与えて早期講和に持ち込もうと考えていたようです。





確かに、ハワイを当時の大和・武蔵等の巨大戦艦で軍事施設を破壊して、攻略することまで、仮に可能だったとしても、戦争はそれで終わりではありません。果たして、日本本土から6500キロも離れたハワイ諸島に食料品や、燃料などを送る貨物船や、タンカーを用意できるほどの国力が当時の日本にあったとは、思えません。間違いなく、アメリカ潜水艦の雷撃の前に10隻中、7~8隻が撃沈されてしまったでしょう。ロジスティックスの維持という基本的戦略視点が全く欠けていた当時の日本には、とても無理な話だったと思えてなりません。
仮に当時の日本がロジスティクスを意識した超優秀な人材だったとしても、米国が潜水艦を大量生産にシフトしてたら詰んでたと思う
護衛戦隊が超優秀でも完全防御は不可能だし、史実の大西洋側みたいに航路を哨戒網で埋めるにしても、太平洋は広すぎる
有能無能関係なく、ミッドウェー・ハワイ方面はどの道詰んでたと思う
(他の方面で決着をつけて、相手の心を折る講話為の一撃なら、可能性はなくも無いが…)
今更なんですが少々調べてみましたので、こちらに書かせて頂きます。
>これに前年と同量程度の取得があっても413万t
>年間取得は199万t(南方油田地帯占領による)
占領地がほぼ存在しない16年と、南方作戦が終了した17年では条件が違い過ぎると思います。
実際の17年の石油還送量は約150万トンですので、後段部分の「油田地帯占領による」との指摘は恐らく違っているかと思います(占領後の施設の再稼働などで本土還送までタイムラグが発生しているためです)。推測ですが戦前の輸入量と混ざっていると思われます。
>1942(昭和17)年の残り石油は320万t前後になってしまい
実際に発動されたMI作戦では60万トンを消費しています。
それでも海軍の内部のみで影響を吸収できた消費量であり、「それに加えてHI作戦で90万トン以上を消費~」という展開ならまだ分かるのですが、仮にMIの消費量を無視するのであれば、HIは30万トン程度消費が増えるだけで可能という事となります。
また、この手の議論にまず出てこないのが真珠湾に備蓄されている燃料で、この年では増減はあれど450万バレル(約62~64万トン程度)が備蓄されています。
この燃料は重油な上、地下タンクにも備蓄されており、また立地上からも仮に敵軍上陸の危機が迫った際に破壊・焼却は難しいもののため、占領の際に接収できる可能性は少なくないと思われます。
全てを変えてしまうような量ではありませんが、一息つける量なのも間違いないかと思います。
今更なんですが少々調べてみましたので、こちらに書かせて頂きます。
>これに前年と同量程度の取得があっても413万t
>年間取得は199万t(南方油田地帯占領による)
占領地がほぼ存在しない16年と、南方作戦が終了した17年では条件が違い過ぎると思います。
実際の17年の石油還送量は約150万トンですので、後段部分の「油田地帯占領による」との指摘は恐らく違っているかと思います(占領後の施設の再稼働などで本土還送までタイムラグが発生しているためです)。推測ですが戦前の輸入量と混ざっていると思われます。
>これに前年と同量程度の取得があっても413万t
>年間取得は199万t(南方油田地帯占領による)
占領地がほぼ存在しない16年と、南方作戦が終了した17年では条件が違い過ぎると思います。
実際の17年の石油還送量は約150万トンですので、後段部分の「油田地帯占領による」との指摘は恐らく違っているかと思います(占領後の施設の再稼働などで本土還送までタイムラグが発生しているためです)。推測ですが戦前の輸入量と混ざっていると思われます。