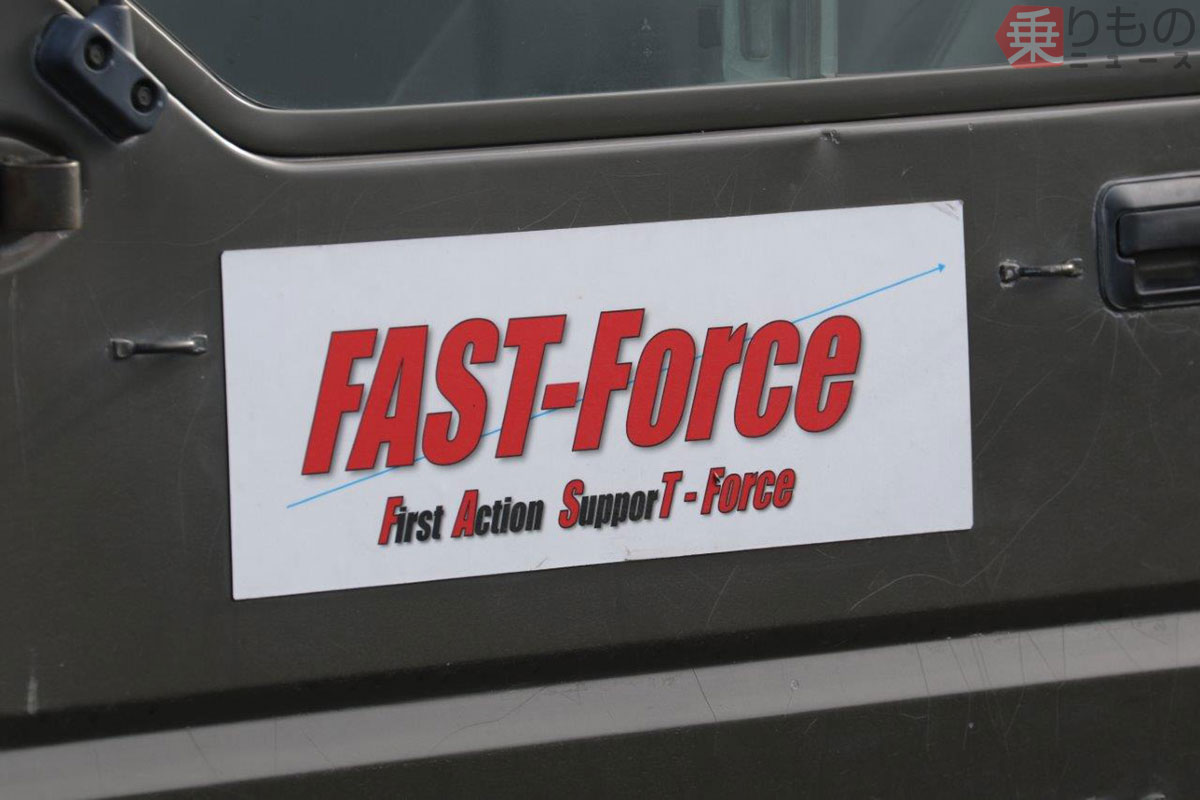乗りものニュース 特別企画
【ミリタリー】急げ、救え! 自衛隊「災害派遣」の現場にせまる!
豪雨や地震など、各地で災害が相次ぐ昨今。行方不明者の捜索活動や瓦礫撤去、被災者への支援など、「災害派遣」の現場で多岐にわたり活動する自衛隊の姿をまとめました。
急げ現場へ! 災害派遣の舞台裏にせまる!
-
日本屈指の大災害として記録されている阪神・淡路大震災で人命救助に尽力した陸上自衛隊は、そのときの教訓を基に災害派遣専用の装備を開発・導入しました。人命救助専用の装備は東日本大震災や能登半島地震などでも活躍しています。
-
自衛隊の災害派遣というと、トラックや重機、ヘリコプターなどが活動するイメージですが、過去には戦車が用いられたこともあります。頑丈とか悪路走破性といった理由はもちろん、それ以外の性能も買われての派遣でした。
-
前身の警察予備隊時代から数えて70年以上の歴史がある自衛隊の災害派遣。2024年の元日に発生した能登半島地震でも派遣され、さまざまな活動に従事しています。自衛隊は災害派遣によって国民の信頼を得るとともに、鍛えられたと言えそうです。
-
2024年元日に発生した能登半島地震に対し、全国から救援部隊が駆け付けました。なかでも自衛隊機で迅速に運ばれたのが東京消防庁と横浜市消防局の小さなレスキュー車。これらは過去の震災の教訓から生まれた特殊な消防車でした。
-
大型艦への給油は大変。
-
固定翼機と回転翼機の長所をあわせ持ち、高速飛行もできるオスプレイは、なぜ能登地方の被災地へ投入されないのでしょうか。それにはやはり、被災地が抱える地理的要因や気候も関係しています。
-
令和6年能登半島地震の被災地に対し、海上自衛隊はエアクッション型揚陸艇(LCAC)を投入して援助を行っています。日本ではLCACの運用開始から四半世紀が経過していますが、後継艇は登場するのでしょうか。
-
能登半島地震で七尾港に災害派遣された大型フェリー「はくおう」は自衛艦ではありません。とはいえ、ただの民間船でもないとのこと。特殊な位置づけのチャーター船、もしかしたら今後増えるかもしれません。
-
熊本地震から5年。いまでは毎年のように自衛隊が災害派遣で活動しています。しかし自衛隊が活動するためには法的な裏付けと出動までの定められたスキームがあります。元陸自トップに災害派遣の流れと課題について話を聞きました。
-
自衛隊の大型輸送ヘリCH-47「チヌーク」が能登半島地震でも多用されています。陸自と空自が保有する、ふたつのローターを備えた特徴あるヘリ。「オスプレイ」が導入されても使われ続けるのには理由がありました。
-
地形が険しい能登半島では、大地震により道路が寸断され、支援の手が滞っています。陸路が使えないなら海路からと、海上自衛隊がホバークラフトを展開していますが、こちらもガンガン送り込めばよいというものでもなさそうです。
-
能登の被災地へいち早く入った自衛艦が、多用途支援艦「ひうち」です。戦闘用ではない小型の艦ですが、ほかの艦にはない能力を生かして、縁の下の力持ち的な存在で活動しています。
-
東京消防庁が能登半島地震への対応として「即応対処部隊」を石川県に派遣しました。この「即応対処部隊」とは一体どういった役目を持つ隊なのでしょうか。
-
ハイパーレスキューも自衛隊機で石川県に向かったそう。
-
長崎県佐世保に所在の水陸機動団などで使用中。
-
ひょっとして初の災害派遣かも?
-
海上自衛隊のエアクッション揚陸艇が能登半島地震で孤立地域への重機や救援物資の輸送で活躍しています。この揚陸艇は一般的な船とは異なる構造ですが、それゆえのメリットがあるとか。ただ運用の岐路に立っている模様です。
-
海上自衛隊で仕事に遅刻すると、「後発航期」と呼ばれるペナルティが付くそう。場合によっては停職処分になるほど重いそうですが、任務の重大さを知るとしょうがないかも。状況によっては、ヘリで送り届けられることもあるそうです。
-
災害発生時、自衛隊のなかで最初に動き出す「FAST-Force」と呼ばれる部隊があります。彼らの担う役割とはどのようなもので、今回の能登半島沖地震ではどのように機能したのでしょうか。
-
2021(令和3)年3月11日で東日本大震災から10年が経ちました。当時、陸自のトップ(陸上幕僚長)だった火箱芳文さんに、被災時の状況や自衛隊の活動について話を聞きました。
-
熊本地震から5年。いまでは毎年のように自衛隊が災害派遣で活動しています。しかし自衛隊が活動するためには法的な裏付けと出動までの定められたスキームがあります。元陸自トップに災害派遣の流れと課題について話を聞きました。
-
自衛隊の災害派遣にも種類がありますが、新型コロナウイルス対策での災害派遣はその要件を満たすのか否か、という声が聞かれます。「災害派遣」の基礎をふまえつつ、議論の争点などを見ていきます。
-
2018年9月に発生した北海道地震では、土砂崩れにより各所で道路が寸断されました。これを復旧すべく、道内はもとより本州各地からも、続々と自衛隊の重機部隊が現地入りしました。民間には見られない重機も活躍しています。
-
自衛隊の災害派遣活動は陸海空それぞれに役割があります。航空自衛隊も様々な役割を担いますが、そのひとつ「輸送力」に注目しました。
-
災害発生時、自衛隊のなかで最初に動き出す「FAST-Force」と呼ばれる部隊があります。彼らの担う役割とはどのようなもので、先の北海道地震ではどのように機能したのでしょうか。
-
掃海艇は本来、機雷の排除を任とする軍用艦艇で、海自の艦艇のなかではだいぶ小柄です。「FAST-Force」に指定された掃海艇「いずしま」の、北海道胆振東部地震における活動を振り返ります。
-
2018年は西日本豪雨や北海道地震など災害が相次ぎましたが、その被災者支援に、貨客船(フェリー)「はくおう」が参加しました。そうしたフネが自衛隊の活動に参加する理由や、船内の様子などを解説します。
-
「平成30年北海道胆振東部地震」に関する自衛隊の被災者支援活動のなかに、「しらせ」の名前がありました。なぜ南極観測船として知られる同船が北海道で支援活動に従事していたのかというと、実はたまたまそこに居合わせたから、という理由でした。
-
「平成30年7月豪雨」の被災地を救援すべく、3万人を超える自衛隊員が派遣されました。その出発前の駐屯地内ではどのような準備がされているのでしょうか。陸上自衛隊練馬駐屯地の様子を取材しました。
「災」の備え、様々な装備品
-
2024年8月31日、およそ8か月半にわたって活動し続けた能登半島地震における自衛隊の災害派遣が終わりました。被害は局所的だったのに、なぜここまで長引いたのでしょうか。また過去には1500日を超える災害派遣もありました。
-
地震や台風などで大規模な災害が発生すると頼りにされる自衛隊の災害救援部隊。ただ、武力事態でもないのに、一般人の土地に無断で入ったり、家屋を撤去したりできるのは、どういった法的根拠からなのでしょうか。
-
市街地上空でも頻繁に見るヘリコプターの低空飛行ですが、航空法で厳格に「最低安全高度」というものが定められています。ただ、その規定が免除になることも。それが人命救助などだとか。自衛隊のヘリコプターを例に説明します。
-
台風や豪雨などではパトカーはおろか、消防車でも救援に向かうことが難しい場合があります。一方で、自衛隊のトラックは東日本大震災の冠水エリアで問題なく走行したとか。なぜ自衛隊のトラックは水に強いのでしょうか。
-
災害発生時、自衛隊のなかで最初に動き出す「FAST-Force」と呼ばれる部隊があります。彼らが担う役割とはどのようなものなのでしょうか。じつは日本全国にある基地・駐屯地で今も待機しています。
-
2024年8月8日に日向灘で発生した地震において、真っ先に航空自衛隊の戦闘機などが飛び立ちました。ただ、戦闘機は本来、領空防衛を担う装備であるハズ。被災地救援できない戦闘機はどのような任務で出動したのでしょうか。
-
令和6年能登半島地震の救助活動で物資などを海上から輸送し、一躍脚光を浴びた自衛隊のフネが「LCAC」です。整備施設を見学すると、つくづくフネらしくなく、まるで飛行機のようでした。その「クセ強感」に迫ります。
-
1958(昭和33)年の年の瀬、大火に見舞われた奄美大島に、空中からパラシュートを使って物資が投下されました。自衛隊初となった、任務としての「物料投下」は、はるばる東京から飛んできたC-46輸送機によって行われました。
-
調達開始以来、約30年にわたって導入されている支援車両が陸上自衛隊にあります。戦闘でも災害派遣でも使えるロングセラーの陸上自衛隊装備、調べてみたら高い汎用性の理由がわかりました。
-
陸上自衛隊の車両は、悪路走破性も重要なため、トラックなども専用のものが多く使われています。救急車も不整地に強い専用のものがありますが、悪路走破性だけでなく収容人数も多いという特徴があります。
-
1990(平成2)年の調達開始以来、約30年にわたって導入されている、そんな支援車両が陸上自衛隊にあります。戦闘でも災害派遣でも使えるロングセラーの陸上自衛隊装備について見てみます。
-
災害派遣時、陸上自衛隊は迅速に出動できるよう、救援資機材をコンテナに収納し、ユニット化した装備を全国の駐屯地および部隊に配備しています。人命救助専用装備の誕生は20世紀末に起きた大規模災害がきっかけでした。
-
2019年10月に起きた台風19号の災害派遣で、陸上自衛隊の「CT診断車」が初めて出動しました。実は民間にもあるというCT診断車ですが、そもそもなぜ陸上自衛隊に配備されているのでしょうか。
-
島しょへの上陸などに使用される陸自のAAV7こと「水陸両用車」は、災害時の活用も期待されます。そうした想定の訓練はすでに開始されていますが、実際に出動となると、まだ解決すべき課題がありました。
-
自衛隊の「災害派遣」は、地震や洪水など自然災害の場合だけではありません。その8割が、実は急患輸送です。消防の行政サービスを自衛隊が肩代わりするようなことをしているのには、もちろん理由があります。
-
戦場はもちろん、地震などの災害時も含め、橋がないからといって立ち止まっていては、計画遂行に支障をきたしてしまいます。なければ架ける、というわけで、陸自の架橋装備を解説します。
-
災害派遣における被災者への入浴支援として、陸自の「野外入浴セット」はしばしば報道などで目にしますが、断水地域で水はどう確保するのでしょうか。入浴支援の舞台裏をのぞくと、自衛隊にしかできないサービスなことがよくわかります。
-
陸自と空自が保有する、ふたつのローターを備えた大型輸送ヘリCH-47「チヌーク」は、導入から30年以上が経過しています。災害報道などで目にする機会も多いかもしれませんが、そのようにいまなおあちこちで使われ続けるのにはもちろん理由があります。
-
2018年現在もなお、陸自では1974年に制式化された「74式戦車」が多数現役です。さすがに第一線での活躍は難しいようですが、運用研究の積み重ねがあったり、戦闘以外にも活用の場があったりして、まだ使いみちはあるようです。
-
自衛隊においても他国の軍隊と同様、食事は最も重要なもののひとつです。そうした意味で陸自の最重要装備ともいえるのが「野外炊具1号」でしょう。そもそもどのような装備で、そしてどのような隊員が調理にあたっているのでしょうか。
これまでの「災」をふりかえり
-
陸上自衛隊の源流は、朝鮮戦争の勃発によって誕生した警察予備隊です。当時は再軍備への懸念から、警察予備隊の出動命令は内閣総理大臣しか出せませんでした。それが、初の災害派遣のときに足かせとなったのです。
-
陸上自衛隊のヘリコプターによる救助活動は、実際のところどのように行われているのでしょうか。2015年9月、関東・東北豪雨にて救助にあたった、UH-60JAの機内の様子を追います。
-
自衛隊の災害派遣というと、トラックや重機、ヘリコプターなどの活動する様を報道でもよく目にしますが、過去には戦車が派遣されたこともあります。頑丈だとか、悪路走破性といった理由はもちろんですが、そこには別の理由もありました。
-
自衛隊にはさまざまな乗りものがありますが、オートバイもその機動性を生かし、多くの現場で活躍しています。なかでも陸上自衛隊の偵察部隊は災害や有事の際、真っ先に現場へ入る地上部隊であり、その任務は危険で過酷なものです。
-
未曾有の被害をもたらした東日本大震災。その現場で輸送ヘリコプター「チヌーク」を駆り、救難活動をはじめさまざまな任務に従事した航空自衛隊の現役パイロットに、当時の様子などを聞きました。
-
2016年4月14日に熊本県で発生した大地震において、真っ先に離陸した自衛隊機はF-2戦闘機でした。これには阪神淡路大震災の教訓が活かされています。